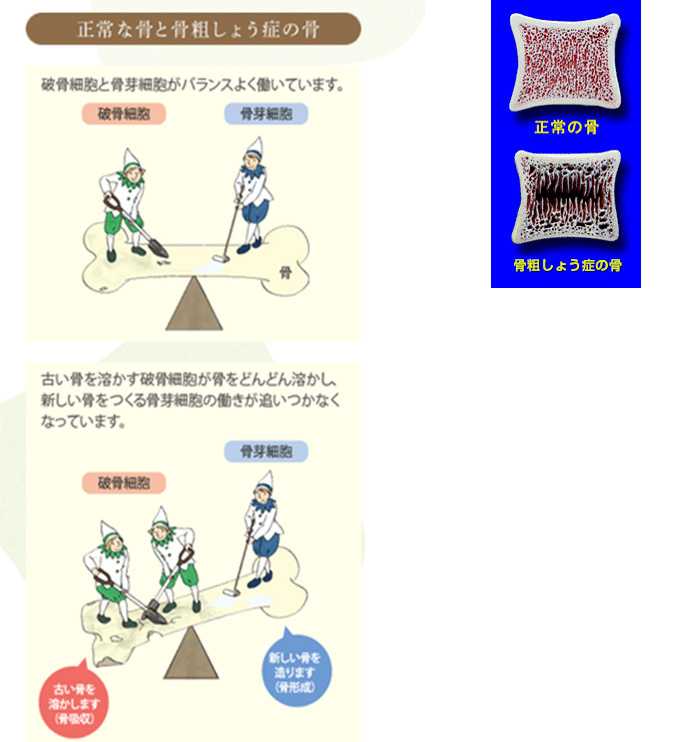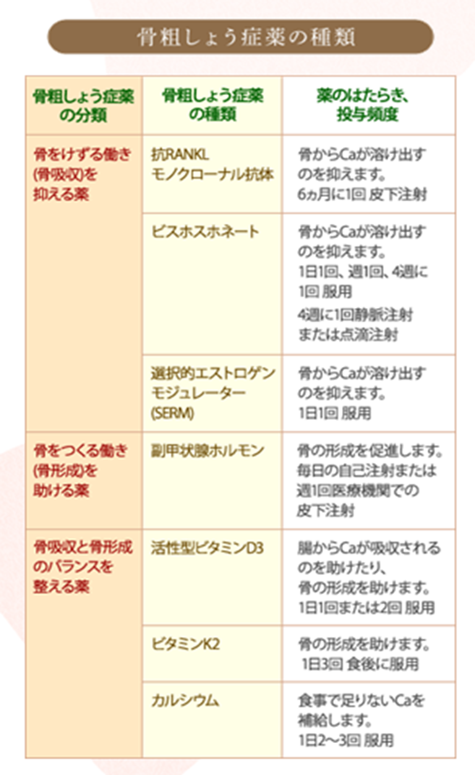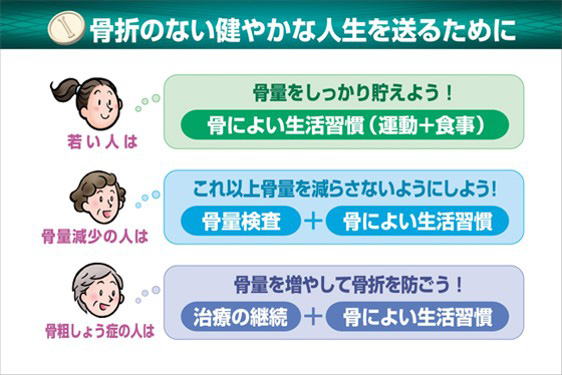膠原病とは
病気は、心臓病や肝臓病といった障害された臓器で大きく分類されます。
その中で、自分の体を自分の体ではないと勘違いして免疫システムが過剰反応してしまう疾患群を『自己免疫疾患』といいます。このような原因で全身の臓器に血管炎をきたす疾患群のことを『膠原病』と呼んでいます。『リウマチ性疾患』や『結合組織疾患』と同意です。
症状
典型的な症状としては、発熱・全身倦怠感・関節症状・皮疹や紅斑・筋肉痛・レイノー現象(指趾末梢が冷感により白色・紫色・ピンク色に変化するもの)や、眼症状(ドライアイ・ぶどう膜炎など)・口腔症状(ドライマウス・口内炎など)があります。もちろん、全ての膠原病に共通して出現するものではありませんし、膠原病に限った症状でもありません。
診断・治療
それぞれの疾患の症状と、検査(血液検査や画像検査)を行います。遺伝子検査や病理診断が必要となる場合もあります。
全身状態から可及的速やかに確定診断から治療まで行う必要性や、特殊な治療が必要な場合は、速やかに専門医のいる大学病院や総合病院へ紹介させていただきます。
症状が落ち着き、近医専門医で対応可能な状況まで回復してきたと判断された時も、当院で引き続き維持療法の継続を行わせていただきます。
また日常の診療は当院で行い、年1-2回の精密検査を大学病院などで行うなどの病診連携も、行っております。
当院で対応可能な主な疾患
- 1.関節リウマチ
- 2.全身性エリテマトーデス
- 3.多発性筋炎/皮膚筋炎
- 4.強皮症
- 5.混合性結合組織病
- 6.血管炎症候群
- 大型血管炎
- 1.高安動脈炎
- 2.巨細胞性動脈炎
- 中型血管炎
- 3.結節性多発動脈炎
- 小型血管炎
- ANACA関連血管炎
- 4.顕微鏡的多発動脈炎
- 5.多発血管炎性肉芽腫症(Wegener's肉芽腫症)
- 6.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
- ANACA関連血管炎
- (アレルギー性肉芽腫性血管炎)
- 免疫複合体性血管炎
- 7.クリオグロブリン血症性血管炎
- 8.IgA血管炎(Henoch-Schonlein紫斑病)
- 9.低補体血症性蕁麻疹様血管炎(抗C1q血管炎)
- 10.抗GBM抗体関連疾患(Goodpasture症候群)
- 免疫複合体性血管炎
- 大型血管炎
- 7.成人型スチル病
- 8.リウマチ性多発筋痛症
- 9.RS3PE症候群
- 10.乾癬性関節炎
- 11.SAPHO症候群
- 12.強直性脊椎炎
- 13.再発性多発軟骨炎
- 14.ベーチェット病
- 15.家族性地中海熱
など
当院で対応不可能な疾患
線維筋痛症